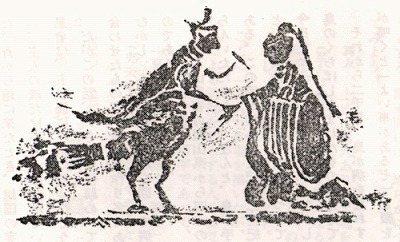初稿 2025年10月25日
最終加筆 2025年11月21日
はじめに言います。
この、しんきゅうカレッジ構想の「本当に言いたいこと」は、
✓ 二つの軸を提供する“場”を作ること
であり、
① 鍼灸治療の全体像を知った上での、基礎力(知・技・見方)を鍛える軸
② 臨床家・事業者としての全体像を知った上で、「どのように生き、どこへ向かうか」に取り組む軸
この二つを鍼灸師が生涯にわたって育てられる環境を作ること。
これが「目的」。
ただし―――
このように言われても、分からない。気づかない。
これを読んでも、ピンとこない。
違いますか?
📄 しんきゅうカレッジ構想書(全文PDF)を読む
※第三章「経済モデル」部分は省略しています。
🟥 鍼灸師は次の事実に”気づけていない“
✓「基礎力が無い」と思っていない
―――だから、
「基礎力を伸ばす場です」
と言っても、刺さらないし、興味も出ない。
鍼灸師の多くは
「臨床に困っている理由は、応用を知らないからだ」
「自分の経験が未熟だから、臨床に困るのだ」
と思っているはず。
確かに、それも一理ある。
でも本当は、
「基礎の理解(臓腑や経絡の意味)が曖昧」
「症状をどう捉えるかの見方が固定されている」
「知識を臨床に“つなげる”力が弱い」
つまり、全体を支えるための、根っこが育っていない。
でも、本人は気づかない。
✓「他の治療観を知らない」とも気づいていない
──だから
「様々な治療観を知り基礎認知を上げる場です」
と言われてもピンと来ない。
多くの鍼灸師は
「自分の治療観が標準だ」
と、心のどこかで思っている。
実際には、
・経絡治療
・中医弁証
・現代医学応用
・筋肉系アプローチ
・運動系
・接触治療系
・あるいは醒脳開竅のような“道具としての鍼灸”
これらが “全く違う言語体系” を持つことを知らない。
「知らないものは選べない」
「選べないものは目指せない」
にも関わらず、
「患者さんに合わせた自分らしい治療を目指す」
ことができると思っているでしょう?
でも、知らないのに。
📄 しんきゅうカレッジ構想書(全文PDF)を読む
※第三章「経済モデル」部分は省略しています
🔷 では、どうしたらよいのか?
まとめてみると、
・原因かもしれない基礎力が弱いことに気づいていない
・治療観の種類を知らないことにも気づいていない
・しかし、困っている
・でも、何に困っているのか、何が必要なのかを言語化できていない
・気づくための、場や体系が必要なのかもしれない
―――だからこそ、この「しんきゅうカレッジ構想」が必要ではないだろうか。
本構想は、鍼灸師が生涯にわたって成長し、学びを継ぎ、次世代に志を渡すための「仕組みと場」の構築を描くものであり、「体系的に学べる場」と「師事して深められる場」が必要と考える。
■ 第一の軸:体系的・段階的に学べる仕組み
鍼灸臨床の「全体像を理解したうえで基礎を鍛える」ことを重視し、
医学・医術・医徳・医業・一般常識・の五つの視点から段階的に学べる体系をつくる。
■ 第二の軸:師事して深める学び
もう一つの軸は、特化した鍼灸臨床を師事的に学べる仕組み。
講師や顧問などに個別に指導を仰ぎ、治療観・哲学・姿勢・修養まで含めた
「伝統の継承に近い深い学び」が可能になる。
■ そして――
この二つの軸を土台に、学び手が互いに刺激し合い、支え合い、成長を分かち合う
「鍼灸師のコミュニティ(場) を形成すること」
これらが、本構想の核となる目的である。
📄 しんきゅうカレッジ構想書(全文PDF)を読む
※第三章「経済モデル」部分は省略しています
本構想のいくつかの目的のもとに、以下の五項目で本文を構成する
1.理念と目的(Why)
・現代鍼灸師を取り巻く課題(離職・孤立・不安定・継承途絶)
・本構想の目的:成長・維持・継続・継承の循環化
・音楽教育モデルをヒントにした二重構造(共学+師事)
・根本理念:「同行二人、自利利他」
・社会的意義:医療文化としての鍼灸の再定位
2.構造と段階制度(How)
・構造図:勉強会と個人指導の連携
・段階制度(初級・中級・上級・助講・講師)
・希望進級制+助講以降の評価制
・OJT・経営教育・倫理教育の内包
・継承儀礼と象徴授与(賞状・バッジ・特殊鍼など)
3.運営と経済モデル(With what)
・会の構成(会長・講師・助講・会員)
・収益源:受講料・認定料・出版物・寄付・共益基金
・配分モデル(運営60/講師30/助講10 など)
・財務の透明化と監査方法
・持続的な人材循環(講師・助講・受講生の回転)
4.教育内容と魅力(What to give)
・知識:東洋医学・現代医学
・技術:鍼灸基礎技術・臨床体系、カンファレンス
・倫理:守秘義務・法務
・経済:治療院経営・税務・広報・価格設定
・修養:養生・対話・祈念・志の継承
・一般常識:OJT・態度・言葉・患者関係
・個人指導:専門知識、専門技術、思想、習慣
5.社会的価値と展望(So what)
・鍼灸師の孤立・社会分断を防ぐ文化的セーフティネット
・医療連携・教育連携・地域貢献への可能性
・収益と文化を両立する循環モデル
・魅力の指標:社会的・人間的・経済的・精神的充足
・今後の課題と展望
📄 しんきゅうカレッジ構想書(全文PDF)を読む
※第三章「経済モデル」部分は省略しています