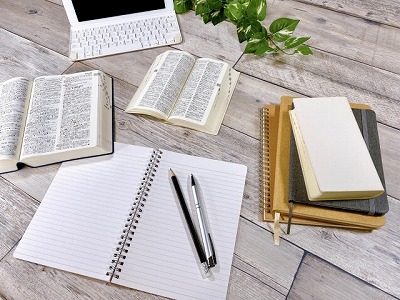★各項目に対する意味や補足は【こちら】をクリックして見て頂くか、「症状の考え方」のページをご覧ください。
初稿2025年1月13日
「食欲不振」から考慮すべき疾患や病態
急性心筋梗塞、心不全、慢性呼吸不全、消化管出血、敗血症、糖尿病性ケトアシドーシス、副腎不全、汎下垂体機能低下症、急性腎不全、電解質異常、劇症肝炎、悪性腫瘍、希死念慮を伴ううつ病、妊娠
ポイント
食欲不振は、この症状単体では危険性のある考慮すべき疾患を判断することは難しい。しかし、上記のような疾患や病態では、食欲不振が起こることがあるので状況に応じて十分に考慮するべきである。
「食欲不振」の中医学としての名称と紹介

納呆(食欲不振)
食欲不振は、「納呆」と呼ばれる。類似症状に「食少」「厭食」「不欲飲食」「納谷不馨(ふけい)」などがある。
「納呆」は、食欲が無くて腹も減らない状態だが、いわゆる食欲不振のように飲食の不振全体をさすこともある。「食少」は飲食量が減少すること、「厭食」は食べることを嫌うこと、「不欲飲食」は食べたいと思わないこと、「納谷不馨」は美味しく感じない、もしくは食欲は無いが食べられることを言う。
納呆には、肝胃不和・脾胃湿熱・胃陰虚・脾胃気虚・脾胃虚寒・脾腎陽虚・傷食などがある。
肝胃不和では、欲求不満などで肝気鬱結し、肝気が胃に横逆して発生する。
脾胃湿熱では、飲食の不節制・脂っこいものや甘いものの過食などによって脾胃を損傷したり、湿熱の邪を感受し、湿熱が中焦に蓄積して脾胃の受納・運化と昇降の機能を失調して発生する。
胃陰虚では、外感熱病の後期に、熱邪によって胃陰が消耗したために発生する。
脾胃気虚では、飲食不節あるいは労倦によって脾胃の気が傷害されて発生する。
脾胃虚寒では、体質が虚弱な人に、飲食の不節制・納涼・冷たい飲物が過ぎるなどの要因が加わって脾胃の陽虚に進行し、虚寒が生じたために発生する。
脾腎陽虚では、なま物や冷たい物の過食あるいは寒涼の薬物の過用で脾陽を傷害し、脾虚が長くつづいて腎陽に波及し、脾腎陽虚となって発生する。
傷食では、飲食物の過剰摂取あるいは消化し難いものを食べて、食滞が生じたために引き起こされる。
気機理論の角度から考察した「納呆」の病機
食欲は、生命活動による気の消耗を補うために発生する。
納呆は、明らかに気の消耗が認められて食欲が発生してもおかしくない状況でも食欲が発生しない、もしくは食べたくない状況と言える。ここで言う気は、水穀の精微とか穀気とか言われているものが主体である。
通常の生命活動なら気の消耗が考えられるのに、実は消耗していなかったときも食欲は発生しない。何らかの原因で気の消耗や排出が減少し、省エネ運転のような状態になり、納呆が発生する可能性がある。
似た状況に、うまく全身へ輸布できなくなっている状況も可能性がある。この場合、気の全体の消費量そのものは減少するので納呆が起こるが、心身の各部位は供給不足によってガス欠状態になる。
全身への清気の輸布は、濁気の排泄と陰陽昇降のバランスを取っているが、濁気の排泄に何らかの障害が起き、結果として清気の輸布がうまくゆかずに納呆へ至ることもある。
臓腑理論の角度から考察した「納呆」の病機
食欲は、気血が不足してくると神に対して食欲を起こさせる。そして、脾胃が動き消化吸収が起こってゆく。
納呆の直接的な直接的な原因は、脾虚か胃実がほとんどである。
脾虚では、運化機能の低下により飲食物の消化機能が低下して発生する。脾胃虚も脾虚胃実も起こる可能性があるが、脾虚をベースにした場合、胃の虚実はどちらでも脾虚の症状がみられる。
脾肝両虚では、肝剋脾が障害を受け、肝の抑制的な調整がうまくゆかずに、脾が亢進したり減衰したりして、脾虚を招き食欲不振にいたる。俗にいう「木克土」は肝鬱によるものとされるが、鍼灸治療の角度から考えると、肝実によって起こっているというよりも、肝の本虚標実になっていることがほとんどなので、ここでは肝虚と表現した。
胃実は、いわゆる傷食で起こる。それ以外にも、胃脘部の痞鞕が続いたのち、胃脘部の筋緊張が亢進してしまい、見かけ上、胃実に見えることがある。
脾腎両虚では、いわゆる陽虚により起こるものがそうだが、脾虚から脾剋腎で腎虚にいたり発生する。命門は全身の陽をコントロールする、つまり動きをコントロールするともいえるので、腎虚は脾虚や胃虚を悪化させる。治療では同治するのが望ましい。
経絡理論の角度から考察した「納呆」の病機
食欲は脾胃の経気が正常に循環していることと、その背景として腎経が正常に循環していることが必要である。
足少陰腎経が乱れると、飢不欲食が起こる。
足太陰脾経や足陽明胃経が乱れると、脾胃の動きも乱れ、納呆などの症状が起こりやすい。
「納呆」に対する弁病施治の鍼灸治療
(1) 百症賦
冷食不化(胃に冷えがあって、食物が消化せず、おくび(げっぷ)・食欲不振・胃部膨満感や疼痛・胸苦しさ・飲食数時間後の嘔吐など):魂門、胃兪
脾虚穀不消(脾土が虚弱で水穀の精微を運化させる機能が変調し、消化不良、食欲不振を起こすこと):脾兪、膀胱兪
2) 勝玉歌
胃冷(胃に冷えがあって、食物が消化せず、おくび(げっぷ)・食欲不振・胃部膨満感や疼痛・胸苦しさ・飲食数時間後の嘔吐など):下脘
(3) 馬丹陽天星十二穴歌
胃中寒(胃に冷えがあって、食物が消化せず、おくび(げっぷ)・食欲不振・胃部膨満感や疼痛・胸苦しさ・飲食数時間後の嘔吐など):足三里
不能食(食欲不振):通里
(4) 長桑君天星秘訣歌
胃中宿食(宿食は脾胃の運化が変調をきたしたり、胃寒によって食物が消化されず脾胃に滞積すること):璇璣、足三里
(5) 針灸配穴古代験方
胃弱不思飲食(胃弱は胃の受納・運化機能が虚弱なこと):足三里、三陰交に針灸
三焦熱邪不嗜食(三焦熱邪は心肺・脾胃・肝腎の熱と同義):関元に灸
飢不能食、飲食不下(飢餓感があるが飲食を受け付けない、飲食しても嚥下困難を起こすこと):章門、期門に針灸
[参考文献]
『診察エッセンシャルズ』日経メディカル開発、監修松村理司、編集酒見英太
『症状による中医診断と治療 上巻・下巻』燎原書店、趙金鐸著
『針灸配穴』天津科学技術出版社、劉天成編著