【注意】趣味の隠し部屋の記事は、基本的に素人がレスポールタイプのギターをいじってみた個人的な備忘録ですので、その辺を踏まえて情報を活用して頂けると幸いです。
初稿 2026年1月30日
レスポールの音質(トーン)と電気回路
✅ 電気回路で変化させる理屈
ピックアップは L(インダクタンス)+R(直流抵抗) を持つ発電機で、そこに
• R(負荷:ポット/アンプ入力)
• C(容量:ケーブル/トーンコンデンサ/配線の寄生容量)
がぶら下がり、結果として
• 共振周波数(どの辺が“キラッ”とするか)
• Q(共振の鋭さ=ピークの立ち方)
• 高域の減衰のしかた(どれくらい丸くなるか)
• 位相の回り方(アタックの輪郭感)
が決まります。
つまりトーンは「部品単体」ではなく L-R-Cの組み合わせで決まります。

▶️ 要素1:ボリュームポットの抵抗値(負荷)=高域の残り方の土台
🔁 何が起きる?
ボリュームポットの値は、ピックアップから見た 並列負荷として効きやすく、共振ピークを 潰す/残すの土台になります。
🔁 傾向
• 300kΩ:負荷が重い → 高域が逃げる → 丸い/太い/ダーク
• 500kΩ:標準 → バランス
• 1MΩ:負荷が軽い → 高域が逃げにくい → 明瞭/抜ける/場合によりキンキン
「音の全体像を変えずに“ハイ落ちを防ぐ”」方向では、まずここが最重要。
▶️ 要素2:ボリュームポットのカーブ(A/B)=“変化のさせ方”が変わる
🔁 何が起きる?
A(オーディオ)/B(リニア)は「抵抗値が回転角に対してどう変わるか」。
結果として 音量だけでなくトーンの変化の出方も変わります(出力インピーダンスが変化するため)。
• Aカーブ:音量感覚が自然。歪み・ニュアンス調整がやりやすい。
• Bカーブ:効く範囲が狭く感じやすい。あるポイントから急にこもる感じが出やすい。
▶️ 要素3:トーン回路(トーンポット+コンデンサ)=高域の逃げ道(可変ローパス)
トーン回路は基本的に
**「高域をコンデンサ経由でアースに逃がす」**回路です。
重要なのは:
• トーンが10でも、トーン回路は 回路上“存在”している(配線・部品の寄生成分も含めて)
• だから トーン撤去/ノーロード(専用ポットあり)にすると、わずかにでも「抜け」が変わり得る
🔁 レスポールで「トーン回路を外す」とトーン10は同じか?
• 同じではない(外すと少し明るく・鋭くなる)
• トーン10でも、トーンポットやコンデンサ、配線の寄生成分が 完全にゼロにはならず、わずかに高域の逃げ道/共振のダンピングが残る
体感表現
• トーン10:10
• トーン撤去:体感的に10.5 くらい(環境によっては分からない程度の場合も)
🔁 「トーン回路が無いと、よりピックアップらしい?」への結論
• 気のせいではない。よりピックアップらしい音になる。
• ただし厳密には「ピックアップ単体の音」ではなく
“周辺回路の影響が減った音”=“加工が薄い音”に近づく。
起きること
• 並列負荷が減る → 共振ピークが鋭く残る(Qが上がる)
• RC回路が減る → 位相回転が減ってアタックがダイレクトに感じる
• 高域の逃げ道が減る → 抜けが良い
注意点
• 生々しさ(弦擦れやピッキングノイズ)も出る
• 逆にケーブル・アンプ・ペダルの影響が目立つ
▶️ 要素4:コンデンサ容量(トーンコンデンサのµF)=“どの辺から落ちるか”が変わる
ここが今回のテーマにおける核心部分。
まず原理(超重要)
トーンを絞ると、コンデンサが効いて 高域を落とす。
その“落ち始める帯域”は、ざっくり言えば
• 容量が大きいほど → もっと低い帯域まで落とす(より太い帯域が暗くなる)
• 容量が小さいほど → もっと高い帯域だけを落とす(上のキラつきだけ削る)
※実際はピックアップのL(インダクタンス)も絡んで単純なRCだけでは決まりませんが、方向性はこれで合っています。
よく使われる容量と聴感傾向(目安)
• 0.047µF(特にシングルで多い):
トーンを絞ると かなり広く暗くなる(“こもる”方向が強い)
• 0.022µF(ハムで定番):
暗くなるが 使いやすい範囲が広い
• 0.015µF / 0.01µF:
“上だけ丸める”寄り。キンキン対策の安全弁として扱いやすい
• 0.033µF:
0.022と0.047の中間。ギター/PUによっては「一番ちょうどいい」ことがある
ハイ寄りの嗜好に合わせたお勧め
• 「普段トーン触らないけど、出すぎた時にだけ丸めたい」なら
0.015µF〜0.022µFが“ブレーキとして上品”になりやすい
• 「いざという時にガッツリ暗くしたい」なら
0.033〜0.047µFが効く(ただしこもりやすい)
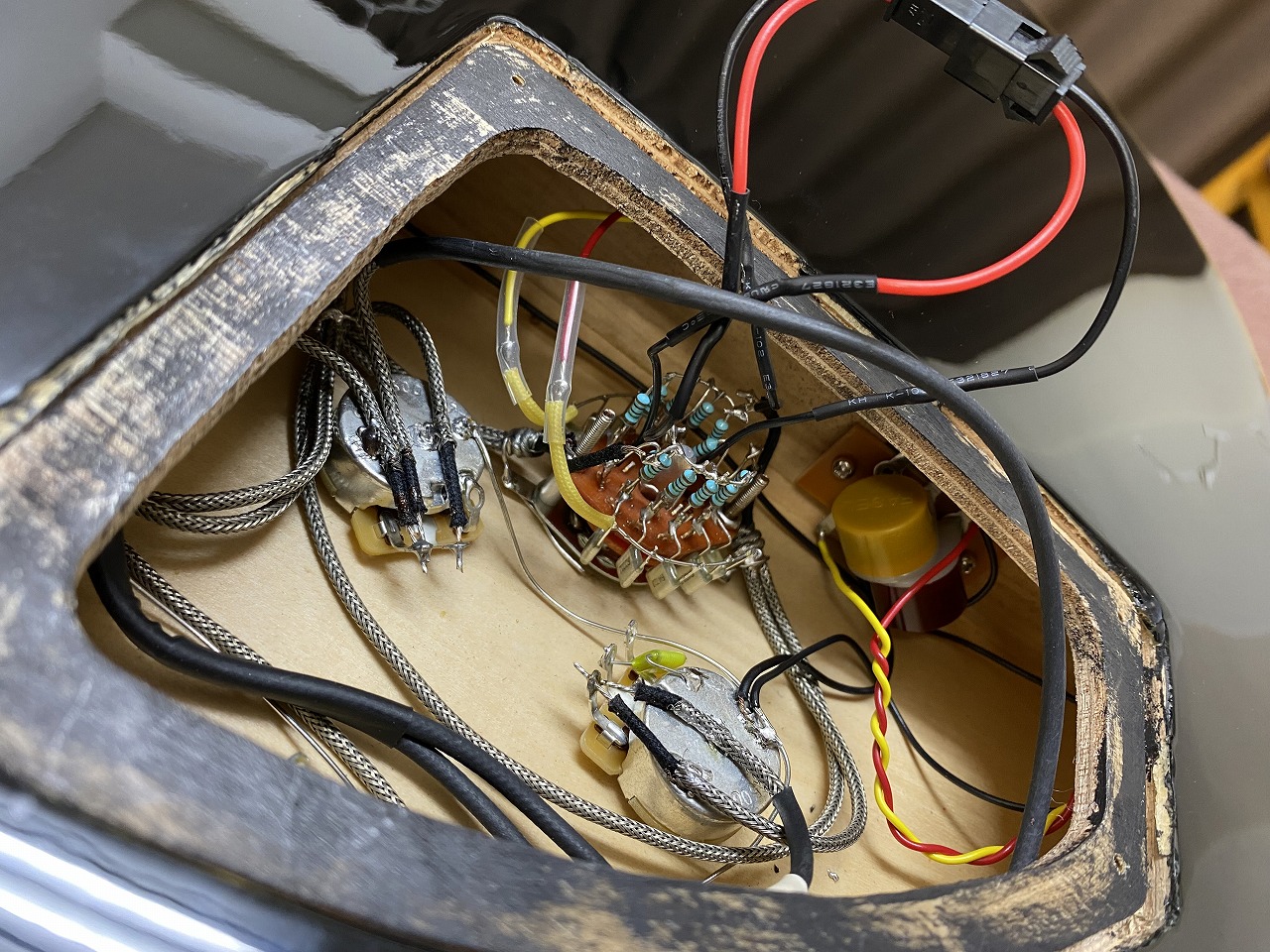
▶️ 要素5:ハイパスフィルター(HPF)は有効か?
• HPFは“ハイを出す主役”ではない
• でも 低域マスキングを整理して、結果としてハイが生きる名脇役になり得る
ポイント
• HPFは高域を持ち上げない。低域を削って相対的に明るく感じさせる。
• 歪み前での低域整理は、分離感・音程感が出やすい。
ただし
• 「レスポール自体のハイを解放する」思想とは違い、
後段で編集する音作りになる(回路的には別アプローチ)。
▶️ 要素6:ケーブル容量(シールド)=“レスポールがこもる”最大の外的要因
ギターの外にあるけど、回路的には超支配的です。
• ケーブルは 容量Cを足す
• ピックアップのLと組んで 共振が動く/高域が落ちる
• 長いほど・容量が大きいほど、ハイは失われやすい
▶️ 要素7:アンプ入力(インピーダンス)やペダルの入力=負荷の追加
アンプや最初段ペダルの入力インピーダンスが低いと、それ自体が負荷になってハイを殺します。
(バッファの有無でも体感が変わる)
✅ 効きやすさ(体感の影響が大きい順の目安)
1. ボリュームポット値(負荷)
2. ケーブル容量(長さ・低容量か)
3. ボリューム位置(出力インピーダンス変化)+ポットカーブ
4. トーン回路の存在(通常/ノーロード/撤去)
5. トーンコンデンサ容量(トーンを動かした時の効き方)
6. アンプ/ペダル入力インピーダンス
7. ハイパスフィルターなど後段整形
✅ ハイ寄りの目的に最短で寄せる「設計手順」
**「全体像は変えずにハイ落ちを防ぐ」「キンキン時に対処しやすい」**を両立するなら:
1. ボリュームを1MΩに(まずここだけ)
2. 「キンキンの安全弁」が欲しいなら
…… トーンは残しつつ、0.015〜0.022µFあたりを検討(“上品に丸める”)
3. さらに“通り道の掃除”を進めるなら
…… ノーロードトーン(10で回路を外す)
4. まだ足りないなら
…… トーン回路撤去(最もダイレクト、ただし荒さも出る)
5. 最後に必要なら
…… HPFで低域整理(編集として)










